私といえば、傑作をしばしば見落としている。
今回は『キッズ・リターン』をようやく鑑賞した。
この映画について語るとき、まず思い浮かぶのは、あまりにも有名なラストシーンだ。というか北野武の映画は、トレイラーの段階でラストをほぼ見せてくることが多い。
それでも映像体験が損なわれないのは、物語よりも空気、時間、距離感を重視しているからであろう。
さて、この『キッズ・リターン』。
物語そのものは、決して特別ではない。
若者の友情、挑戦、挫折。
そして、未熟ゆえの愚かさを描いたものだ。
落ちこぼれのマブダチが拳闘に足を踏み入れ、ちょっとしたズレによって悪い方向へと流されていく。
二人とも徹底して未熟だ。だからこそ普通の青春を生きられなかった若者の孤独や焦燥が、妙に刺さる。
シンジとマサルは、ほとんど愛し合っているといってよい。
親友であり、兄弟のようにベッタリでありながら、シンジはマサルに対して敬語を使う。
マサルのほうが若干背が高いし、ダブリなのだろうと勝手に補完している。
この、ほとんど対等なのに微妙な上下が残る関係こそが、シンジの”悪い先輩依存”を形成している。
カツアゲする時の実行犯はマサルで、シンジは見ているだけだ。ヤクザに突っかかっていく度胸があるのもマサル。
一方シンジは、そこまで暴力的な振る舞いを見せない。悪い子ではないし、むしろ真面目な印象さえ受ける。
しかしシンジは、主体性が無いのである。
だから悪い方向へと自分を引っ張ってくれるマサルを、明らかに求めている。
そしてなぜか、悪い方向にだけ吸い寄せられる。
まるで「悪い兄貴分」に導かれることでしか、自分の存在を確認できないかのように。だから落ちこぼれだし、不良。
マサルが居なくなってからも、その影響は色濃い。
シンジは”悪のメンター”ありきでないと行動できず、悪い先輩に流されてしまう。せっかく良いところまで行ったボクシングも、そのせいで辞めてしまう。
しかしこの二人は、本質的にはダメでも落ちこぼれでもない。
マサルは粗暴で短絡的だが、要領が良く行動力もある。
思い付きでボクシングを始めて、素質がないことを悟りさっさと辞める。
ヤクザの世界に飛び込めば短期間で頭角を現し、再会時には就活して社会に戻ろうとしていた。
シンジは主体性がなく悪に流されやすいが、才能のある人間だ。
ボクシングを始めてすぐに筋の良さを見せて、高校も卒業した。まともな環境にいたら、普通に道が開けるタイプだったろう。
二人とも、表面ほどダメな奴ではないのである。
それなのに、なぜあれほどの閉塞感が漂うのか。
それは当時の社会が、「勉強ができなければ終わり」という価値観を平然と押しつけていたからだと思う。
今のように進路の自由があるわけでもなく、レールから一度外れた若者に、世間は厳しかった。やり直しの選択肢が少なく、サラリーマン的な生き方が是とされたのである。
シンジとマサルの焦燥感は、彼ら自身の愚かさよりも、むしろ時代そのものの閉塞感に由来しているのではないだろうか。

バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。
この言葉は、どの年代で聞いても刺さる。
十代なら希望として、大人になれば痛みとして、歳を重ねれば切なさとして。
だが、あの二人に関して言うなら、この言葉は比喩でも虚勢でもなく、本当にまだ何も始まっていない。
だから本人たちがどう思っているかはどうあれ、自嘲でもなんでもなくただの事実なのである。
道を踏み外したように見えても、それは単に若さゆえの迷走であり、未熟ゆえの遠回りに過ぎない。
シンジにもマサルにも、才気がある。
どちらもまだ本当のスタートラインには届いていない。
『キッズ・リターン』は、まだ始まってもいない若者たちの物語そのものだったのだと思う。
ただし、最も残酷な見方をするなら、本当に終わっているとも言える。
シンジが急に主体性を持つことは難しいだろうし、背中に刺青があり左手がダメになってしまったマサルの予後は、どう考えても厳しい。あの時代、底辺から成り上がる手段は少ない。
しかし、あのラストの爽快感。
映画全編で漂っていた息苦しさが、あの瞬間だけふっと解ける。
終わりなのに始まりのようで、敗者なのに清々しい。
あれこそが青春の一瞬だけ持つ、不可思議な輝きなのだと思う。
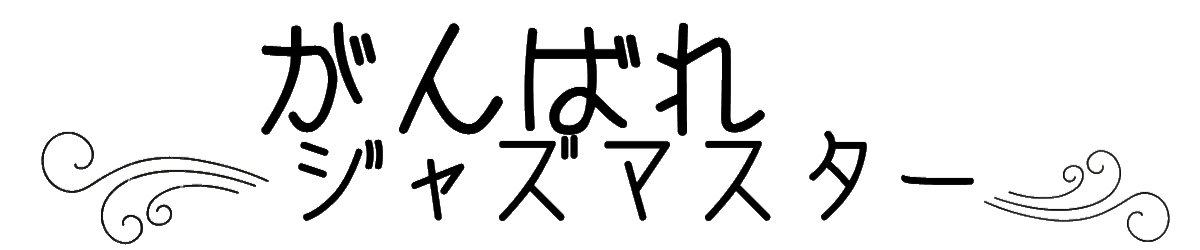









コメント