
年末に入ると、未視聴の映画を消化し始めるのが私の癖だ。
今回は、『菊次郎の夏』を観た。
見終わった直後は、正直「あんまり面白くなかったな」と思った。
旅の目的は達成できないことが早い段階で分かり、二人は肩を落とす。
そこから先の大半は、菊次郎が正男を元気づけるために、ただ遊びまわるだけのシーンで構成されている。
こうした無為なシーンを恐れずに撮るというのは『ソナチネ』でも用いられた手法である。
そこで私は気が付いた。
ハイライトに残らないような無駄な時間こそが、実は人生の主体なのだ。
そう悟った瞬間、映画に対する評価は反転した。
両親が不在で、祖母と二人で暮らす正男には、どうしても“父性”のようなものが必要だった。
たとえそれが、菊次郎のようなボンクラであっても。
いや、この場合はボンクラのほうが良かったのかもしれない。
菊次郎はヤクザ崩れの不器用者で、ヒッチハイクひとつまともに頼めない。
自作自演をしたり、盲目のフリをしたり、「乗せろよコノヤロー」と恫喝するしか能がない。
しかしそんな彼も、正男と関わるなかで、確かな善性や父性を見せるようになる。
別れた後、ちょっと寂しそうな菊次郎の背中。
正男を見守る、菊次郎の眼差し。
実はこの旅路に愛着を持ち、真に救われていたのは正男よりも菊次郎の方だったのだ。
だから『菊次郎の夏』。
冒頭に繋がるラストシーン、正男の足取りは軽い。
あの帰り道の軽やかな足取りこそ、この映画が語る核心であろう。
母には会えなかった。
旅は目的を果たせなかった。
失敗に終わっているはずなのに、正男の身体は全く悲しんでいない。
以前よりも力強く、世界を知った子どもの歩みになっている。
行きずりの変な大人たちとの出会いはそのほとんどが無駄で、意味がなく、くだらない。
その無駄な時間こそが、正男を確かに成長させたのである。
「陰気臭えガキ」と言われた正男の姿はすでに、無い。
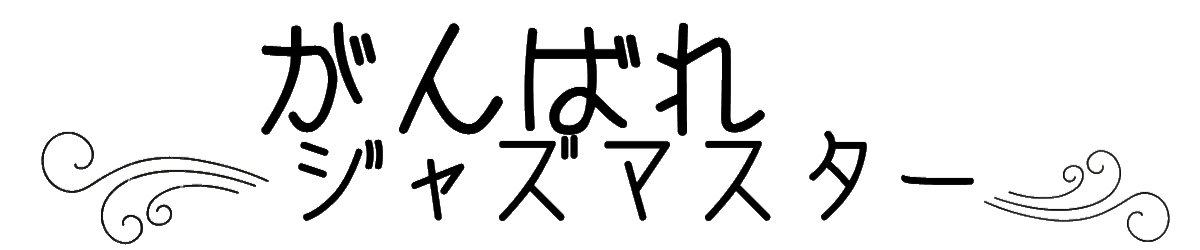




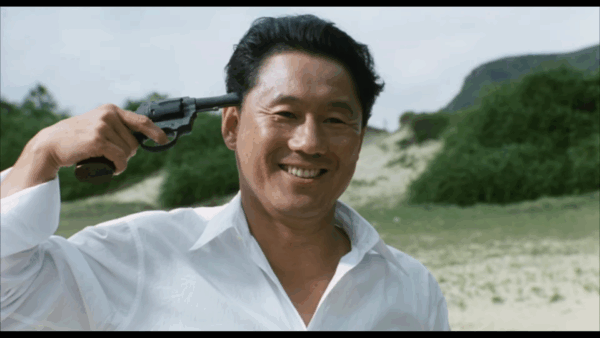
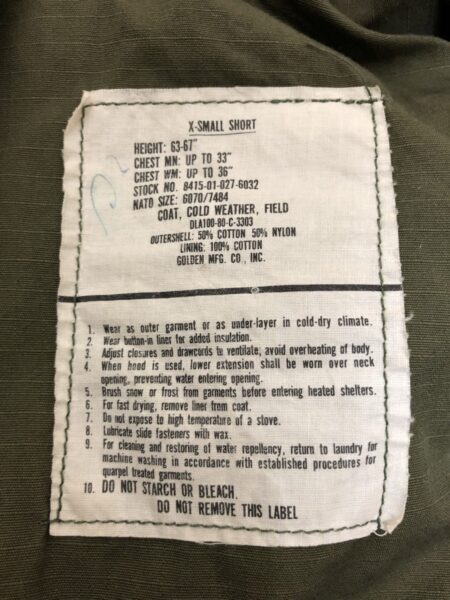




コメント