スランプである。
ちなみに私はプロでもないし、アマでもない。要するに、ギタリストではないのだ。
だがギターを買って、眺めて、いじって、音を作る事が好きである。
久々にアンプで音出しをしてみたところ、再認識。
「音、イマイチだな・・・」
無論、私の技術が未熟なせいもある。
しかし、この妙にチャキチャキとしたアタック感の強い音は、今の私を満足させるサウンドでは無かった。
一説によると、USA製はそんな事は無いらしい。が、比較した事がないので分からない(私のはMade in Japan Heritage)。
基本的に、シングルコイルというのはパワーが控えめである。
パワーが低いのは悪いことではなく、そのクリーンなサウンドに需要があるのだ。
しかし私はグレッチの豊潤なサウンドに慣れてしまったせいか、ジャズマスターのソリッドなサウンドが合わなくなってしまったのかもしれない。
それを嘆いていても仕方がないので、音作りについて考えてみる。
アンプ側でトレブルを削る
まあ、これは基本的な事だろう。
ローをブーストするよりもトレブルを削ったほうが効果が分かりやすい。
しかし狙った音域がなかなか減衰しないので、思いっきり削ることになる。
ギターのトーンを絞る
これは、あまり有効ではなかった。
ハイが落ち着いてくる頃には、全体が籠って使い物にならないサウンドになってしまうのである。
ギターのボリュームを絞る

やっぱり、これか。
実際、ジャズマスターのボリュームを絞る人は多い。
その理屈はハイ落ち。
ボリュームを絞ると、高音域のほうが優先してアースへと捨てられていく。
その途上、ボリューム”8″くらいでいい感じにカドの取れたサウンドになるというわけ。
その分アンプのマスターを上げよう。
ハイ落ちの仕組みについては、以前の記事にも書いた通りだ。

プリセットスイッチを使う
最近ハマっているのがこれだ。プリセットスイッチは上位置でON。
かつては全く需要の無かった機能だが、今使ってみると案外悪くないことに気が付いた。
これをフルテンにすれば、アンプ側がフラットでも太めのサウンドが出た。
フルテンでもマスターの回路と音が違う理由は、ポットの定数が異なるためだ。
マスター側のトーンポットは、1MΩ。
対してプリセット側のトーンポットは50kΩ。
抵抗値が低いほど高域が大きく減衰するため、プリセットスイッチONだとウォームなサウンドになるというわけだ。
まとめ
やはりジャズマスターは、一筋縄ではいかなかった。
フルテンにして適当に弾けば良いわけではないことを痛感。
まあエフェクターでどうこうするという手立てもあるが、私は出来るだけ原音の段階で何とかしたかったのである。
やはり手のかかるギターであったことに、私は安堵した。
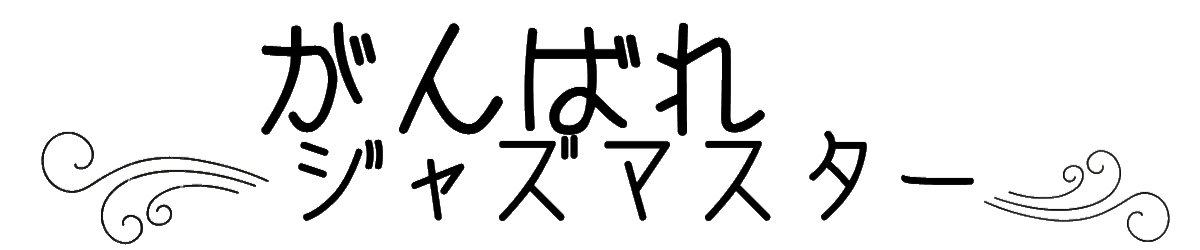









コメント